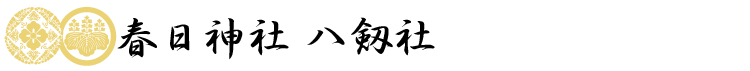七五三のご案内

七五三を迎えられたお子様、ご家族の皆様へ
心よりお祝い申し上げます。
春日神社では、氏神様への感謝とこれからの健やかなるご成長を祈念する七五三詣のご祈祷を、下記の通り奉仕いたします。
お子様の晴れの日が、心温まるひとときとなりますよう、神職一同心を込めてお迎えいたします。
【ご予約不要のご祈願日程】
日時:令和7年11月 1日(土)・ 2日(日)
8日(土)・ 9日(日)
15日(土)・16日(日)
29日(土)・30日(日)
受付時間: 午前10時から12時(予約不要・随時受付)
祈祷料:お子様1名につき5000円
※お守り・千歳飴などを授与いたします。
<その他のご予約不要な受付日>
・10月19日(日)午前10時から11時
・10月26日(日)午前10時から11時
【ご予約による個別祈願をご希望の方へ】
上記日程以外でも、ご希望に応じて個別での七五三詣のご祈祷を承っております。ご家族のみのご案内や、カメラマンによる撮影をご希望の方にも対応可能です。
ご予約は、下記の「御祈願予約サイト」より24時間受付しております。
(カレンダー上に表示される空き状況を確認してご予約ください)
また、お電話・お問い合わせフォームからもご予約いただけますので、ご都合に合わせてお申し込みください。
七五三祈祷の流れ
神社にてご祈祷を受けるまでの流れをご説明いたします。

特設テントで受付もスムーズです。
受付
当日は拝殿横の特設テントにてご祈祷受付をいたします。
その場で受付用紙をご記入いただき、ご祈祷料をお納めください。
順次ご祈祷を行っておりますが、最大で30分程度お待ちいただく場合がございます。
特設の待合所も設置しております。

春日神社拝殿内の様子
ご祈祷
ご家族そろって春日神社拝殿に上がっていただきます。
式の中でお子様一人ひとりのお名前を神様に申し上げ、これまでのご加護に感謝を伝え、今後の健やかな成長をお祈りいたします。
その後、お祝いされるお子様一人ひとりに玉串(たまぐし)をお渡しし、ご神前に捧げていただきます。その後、ご家族そろって「二礼・二拍手・一礼」の作法にてお参りしていただきます。

"写真は家族のたからもの"
記念撮影お手伝いいたします。
気軽にお声がけください。
直会(なおらい)
ご祈祷が終わるとお下がりとして、お守りや千歳飴等の授与品をお渡しいたします。
また直会(なおらい)として、米菓子やお神酒をお召し上がりください。
ご祈祷料一覧表
| 1名 | ¥ 5000 |
|---|---|
| 2名 | ¥ 9000 |
| 3名 | ¥12000 |
ご兄弟も合わせてお参りされる場合は、割引になります。

基本は数え年でお祝いしますが、満年齢でもご奉仕いたします。
※数え年とは、生まれた年を1歳と考え、新年(1月1日)を迎えるごとに、年を取る年齢の考え方です。
例、令和6年12月23年生まれの人は、令和7年中は数え年で2歳になります。
七五三コラム 髪置(かみおき)・袴着(はかまぎ)・帯解(おびとき)

女子七歳、男子五歳、男女三歳の子どもが着飾って氏神さまを参拝する現在の七五三詣は、昔の髪置・袴着・帯解などの祝いから発展したものです。
<髪置(かみおき)>
髪置(かみおき)は、男女ともにそれまで剃っていた頭髪を伸ばし、整えはじめる儀式です。三歳までは頭頂部の髪を残し剃ってしまいましたが、髪置(かみおき)を終えると大人と同様の髪型が出来るようになりました。昔は乳児の頃に髪を剃ることで、健やかな髪が生えてくると信じれらておりました。
<袴着(はかまぎ)>
袴着(はかまぎ)とは初めて袴を着ける祝いで、平安時代にはすでに行われておりました。当時は男女とも袴を着けたのですが、江戸時代に庶民の間に流行するようになってからは、男児の祝いとなり年齢も五歳に定まりました。
宮中では「着袴(ちゃっこ)の儀」と呼ばれ、当時と同様男女の別なく行われています。
<帯解(おびとき)>
帯解きとは、帯の代用である付紐を取り去り、大人と同じ帯を着用することです。
幼いうちは着物に付紐をしますが、成長すると付紐を取り去り、衣服の脇をふさぎ帯を着用しはじめます。すでに室町時代には行われていたようで、当時は九歳でおこなっていましたが、江戸時代末期からは七歳の祝いとなりました。
これらのお祝いはいずれも月日が一定していませんでしたが、天和元年(1681年)11月15日の吉日に五代将軍徳川綱吉が子の徳松の祝儀を盛大におこなってからは、11月頃に行われるようになり、そして名称も総称して七五三詣と呼ぶようになったようです。
三歳、五歳、七歳は医学的に見ても子どもの発育上の段階であり、三歳で言葉を解し、五歳で知恵付き、七歳で歯が生えかわります。その一面いろいろな病気にもかかりやすく、種々な危険の伴う大切な時期でもあります。この時期に健全な成長を神さまに祈ることは、親心の自然から起こったものであろうと思います。
七五三の文化は「子孫愛護」と「敬神崇祖」が結びついた、わが国独特の極めてゆかしい伝統であると思います。
七五三の日、父母と共に神前に手を合わせた思い出が子どもの糧になり、その一生を楽しくさせるものではないでしょうか。
七五三コラム 千歳飴(ちとせあめ)

千歳飴は、元禄の頃に浅草などで売り出された千年飴が始まりとされており、子の長寿の願いを込めて細く長く、また縁起が良いとされる紅白になっています。
袋も長寿の縁起物とされる「鶴亀」や、冬でも緑を保つ「松」や「竹」、冬を耐えて真っ先に花を咲かせる「梅」の「松竹梅」などの縁起の良い絵柄が描かれています。